
ノロウイルスといえば冬に流行する感染症の一つで、流行の目安は、11月〜3月っていわれています。
ノロウイルスは低温や乾燥に強く、ちょうどこの時期に流行するのですね。
牡蠣などの二枚貝はノロウイルスを貯めやすいといわれていて、生で食べる機会が増えることも流行の一因になっているようです。
管人も介護の仕事をしていたときはノロウイルスには特に気をつけていました。
とくにノロウイルスは人から人への感染が多い!ということで感染者が出たら大変なことになりますからね。
そんなノロウイルスについて介護の勉強会で学んだことを書いていこうと思います。介護の現場で働く人も、そうでない人もノロウイルスのことをしって予防したいですね。
目次
感染予防対策は
まずは、予防することが最優先ですね。
ノロウイルスの感染予防についてのポイントを一緒にみていきましょう。
基本は手洗いです
石鹸と流水でこまめにおこないましょう。
調理や食事の前や、トイレ、オムツ交換、汚物処理の後には必ず念入りにおこないう事がたいせつですね。
洗い方のポイントは、時計や指輪も外して指先、爪の間、指の間、親指、手首もしっかりと洗うこと!
最後に蛇口も石鹸で洗ってペーパータオルなどで手をしっかり拭いて捨てることも重要です。
余計なところに触らないことが大切なんですね。
とても分かりやすい手洗いの仕方の動画がありましたのでご紹介しておきますね。
食品からの感染を防ぐための対策は

牡蠣などの二枚貝などと、サラダなどの加熱しない食品や、調理済みの食品を接触させないことが大切です。
調理の順番を考えて最後に使用したり、その後しっかり手洗いをするようにしましょう。
厚生労働省の指針は以下のようになっています。
一般的な感染症対策として、消毒用エタノールや逆性石鹸(塩化ベンザルコニウム)が用いられることがありますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法としては、次亜塩素酸ナトリウム※や加熱による処理があります。
調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※(塩素濃度200ppm)で浸すように拭くことでウイルスを失活化できます。
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。
なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具(まな板、包丁等)を使用するか、調理器具を使用の都度洗浄、熱湯消毒する等の対策により、他の食材への二次汚染を防止するよう、特に注意するよう気をつけましょう。
身近な人がノロウイルスに感染したら
身近な人がノロウイルスに感染したらどうしたらよいのでしょうか?
ノロウイルスに感染すると突然嘔吐したりすることがあります。
慌てずに対処していきましょう。
おう吐や下痢が起こったら
おう吐が起こったら慌てずに手早く対処することが大切です。まずは手順をみていきましょう。
- 人を遠ざけ換気する
- 床が汚れを掃除する
- 汚れた衣服やタオルを洗濯する
- 感染した人が触れたものを消毒する
- 捨てられるものは捨てる
それでは順番にみていきましょう。
人を遠ざけ換気する
人を遠ざけて換気をしましょう。
次に掃除や消毒をする際は、使い捨て手袋やマスクを使用して直接触らないことが大切です。

床が汚れを掃除する
汚れをペーパータオルで覆って嘔吐物が飛び散らないようにしましょう。
そして、塩素系漂白剤の希釈液を染み込ませて静かに拭き取るようにしましょう。
強く拭いたり、掃除機で吸い込もうとするとウイルスを舞い上げてしまい、感染源を拡げてしまう可能性があるのでとても危険です。
最後に塩素系漂白剤の希釈液で消毒をしましょう。
汚れた衣服やタオルを洗濯する
洗剤で静かに手洗いをします。
塩素系漂白剤の希釈液に浸してから、もう一度洗濯します。(他の洗濯物と分けて洗うこと!)
感染した人が触れたものを消毒する
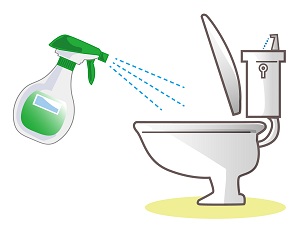
トイレや洗面所、食器や触ったドアノブなどを塩素系漂白剤の希釈液で拭いて消毒しましょう。
捨てられるものは捨てる
掃除に使った手袋やマスクなど、捨てられるものはビニール袋に入れて密閉して燃えるゴミに出しましょう。
この際、捨てるゴミにも塩素系漂白剤の希釈液をかけておくとゴミから感染が拡がるのを防ぐことができます。
ゴミ袋を縛る時は、中の空気を抜かないようにしましょう。
袋を潰してしまうと、ウイルスを撒き散らしてしまいますよ。
感染経路は?

ノロウイルスがどういう経路で感染するのかを知っておくことも大切ですね。ノロウイルスの感染経路別の対策も見ておきましょう。
- 食事を介して感染するケース
- 人から人へ感染するケース
- 手から口への感染するケース
- しぶきを吸い込むことで感染するケース
- 汚染した環境を介して感染するケース
主なケースはこの5つです。それぞれの具体的な内容と対策を順番に見ていきましょう。
食事を介して感染するケース
ノロウイルスに汚染された食品を生や加熱が不十分な状態で食べる。
食品別に見ると、ノロウイルスを溜めやすい牡蠣などによる感染が多いといわれています。
人から人へ感染するケース
ノロウイルスに感染した人が扱った食品を食べることで感染します。
元になる食品を収穫する時、加工する時、調理する時、などが考えられるので気をつけましょう。
手から口への感染するケース
感染者が吐いたおう吐物や便に手で触れて、ノロウイルスが付着した手から口を介して体内に入ることで感染します。
しぶきを吸い込むことで感染するケース
ノロウイルスに感染した人は、突然おう吐することがあるんですね。
そのとき近くにいる人がしぶきを吸い込んで感染してしまうことがあります。
汚染した環境を介して感染するケース
ノロウイルスに感染して人が使ったトイレや洗面所、食器や触ったドアノブなどから感染することもあります。
ノロウイルスに感染するとどうなる?
口から感染したノロウイルスは小腸で増殖を始めます。
感染してから1日〜2日の潜伏期間を過ぎると体がノロウイルスを外に追い出そうとします。
それが強い吐き気やおう吐、下痢の症状として現れるのですね。
多くの場合、症状は1日から2日で自然に回復するそうです。
ただし、乳幼児や高齢者など体の弱い人が感染すると、症状が長引くことも!
おう吐や下痢が続くと水分が失われるので、脱水症状を起こしやすいです。
点滴や入院が必要になることもあります。
高齢者の場合には、おう吐物が気道に入ってしまうことがあり、誤嚥性肺炎や窒息を起こすこともあり注意が必要です。
おう吐物が喉に詰まった場合は救急処置が必要な為、すぐに救急車を呼ぶことが必要になりますね。
受診が必要な場合は
救急車を呼ぶほどでもないけど心配なときもありますよね。
どんなときに医療機関を受診したらよいのでしょうか?
脱水症状がひどくなる前に受診を!
- おう吐が半日〜1日以上続く場合。
- 乳幼児はぐったりしている時。
すぐに救急外来か救急車を呼ぶ場合
- 尿が半日以上出ない時。
- 尿の色が濃い時。
- 唇がカラカラに乾いている時。
これらの症状が現れたら躊躇せず救急車を呼びましょう。
当ブログでは、ノロウイルスに感染した際の出勤停止に関しても記事を書いています。よかったら参考にしてみてくださいね。
まとめ
ノロウィルスはとても感染力が高い病原菌です。
特に寒くて乾燥する季節は、そのリスクが高くなります。
今回紹介した対策を常に意識して、しっかりと感染を予防してくださいね。
【ノロウィルスの感染予防対策】
・手洗い
時計や指輪を外して、爪の間や手首までも綺麗に洗う。
・食品の調理法
ノロウィルスに感染しやすい食品(牡蠣などの二枚貝)と、調理済みや生で食べる食品を一緒にしない
・アルコール消毒は効果なし、ハイターなどの次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒しましょう。
・加熱は85度で1分間以上行う。
ノロウィルスは、対策をしっかりすれば決して怖くはありません。
家族など身近な人がかかっても慌てることなく感染を最小限に食い止めるよう冷静に対処していきましょう。










