3月3日はひな祭りですね。
上巳の節句(じょうしのせっく)と呼ばれ、五節句の一つとされています。
桃の節句とも呼ばれ、女の子が健やかに成長し、良縁に恵まれ幸せになることを願う行事として知られていますね。
この。ひな祭りですが、歴史は古く平安時代まで遡るとされています。
五節句とは、もともとは中国の当の時代に奇数の月と日にちを取り出して、災いを祓う祭事を行っていました。これが、日本に伝わり広まったものです。
- 1月7日 人日の節句(じんじつ)七草粥を食べて無病息災
- 3月3日 上巳の節句(じょうし)桃の節句、ひな祭り
- 5月5日 端午の節句(たんご)子供の日、男の子のお祝い
- 7月7日 七夕の節句(しちせき)短冊に願いを込めて
- 9月9日 重陽の節句(ちょうよう)宮中や寺院で菊を鑑賞
目次
ひな祭りの由来とは?

ひな祭りは、「流し雛」と「ひいな遊び」という二つの風習が結びついてできたといわれています。
流し雛とは、人が己の穢れを紙の人形に移し、それを自分の身代わりとして川に流すという風習です。
ひいな遊びは、平安時代に上流階級の女子の間で、紙で作った人形を使って‘‘ままごと遊び”がはやっていたようです。
それが、江戸時代になると宮中行事の雛祭りとなり、庶民の間にも広まっていったといわれています。
江戸時代中期には、段飾りが登場し、現在のひな祭りの原型になったのでしょう。
明治時代になると農村部まで普及し、現在に至るというわけですね。
なぜ、ひな祭りには桃の花を飾るのでしょうか?
ひな祭りは「桃の節句」とも呼ばれます。
由来は、古代中国にまで遡ります。
古代中国では桃の花には厄払いや魔除け、長寿をもたらす力があると信じられていました。
そこで、桃の花を飾り、桃の花びらを浮かべた桃花酒(とうかしゅ)を飲んだり、桃の葉をお風呂にいれて入ったりしていました。
こうして古代中国の人たちは、3月3日に無病息災を願っていたのですね。
ひな祭りといえば、ちらし寿司に、ハマグリのお吸い物、雛あられや菱餅などが知られていますね。
なぜ、ひな祭りにこれらの食べ物をたべるのでしょうか?
ちらし寿司
ちらし寿司の具には「海老」や「レンコン」「まめ」などがを使われますね。
海老は、腰が曲がっているため長生きの象徴とされています。
レンコンは、見通しがよい。豆は健康でマメに働ける、などの意味があり「ひな祭り」にふさわしいといとされています。
ハマグリのお吸い物
ハマグリは、平安時代の”貝合わせ”遊びでも知られていて、2枚の貝殻がピッタリ合わさっていて、他のハマグリの貝殻を1枚を持ってきても絶対にピッタリ合いません。
このことから、夫婦円満で一生一人の人と添い遂げるようにとの願いが込められています。
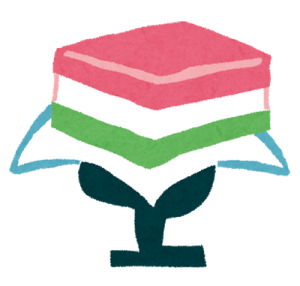
菱餅
菱餅は3色のひし形に切ったもちを重ねたものですが、この3色にも意味があります。いくつかの説があります。
ひとつは、
- 緑は、健康や長寿
- 白は、清浄
- 桃色は、魔除け
もうひとつは、
- 緑は、大地
- 白は、雪
- 桃色は、桃の花
を意味し、雪がとけて大地に新芽が芽吹いて、桃の花が咲く、という意味が込められているという説があります。

雛あられ
雛あられは菱餅を小さく切って砂糖を塗して揚げたものです。
3色の由来は菱餅と同じです。
まとめ
ひな祭りの由来ってとても深いですね。日本の風習がどんどん廃れていく昨今、子供に風習の意味を伝えていくのは私たち大人責任ですよね。
この記事を書くにあたり、いろいろ調べてみて、大変勉強になりました。
今年のひな祭りにはしっかりと「ひな祭り」のことを伝えたいと思います。











