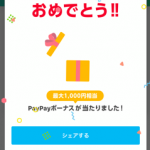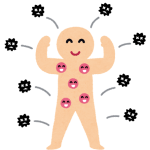猫好きの管理人は、ノラ猫でも飼い猫でも見かけるとついつい頭をなでてしまったりするのですが、先日とてもショッキングなニュースを耳にしました。
厚生労働省から発表されたニュースによると、2017年/7月24日、野良猫にかまれた50代の女性がマダニが媒介する感染症である 「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症し、10日後に死亡していたというのです。
通常、人がマダニに刺された際に感染するとされているSFTSウイルスが原因なのですが、猫からヒトへの感染事例が明らかになるのは初めてとのこと。
ところが最近になって新たな事例が発表されました。
2017年10月11日に報道されたニュースで、日本で初めて飼い犬から人へのSFTSの感染が認められたと発表がありました。
飼い犬と接触した徳島県の40代男性が、マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症していたとの発表した。

出典 https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html
この病気の原因となるマダニは草むらなどに生息しており、ハイキングなどで森林に入り刺されることが多いといいます。
猫から感染することは少ないようですが、夏休みや行楽シーズンに子供が山や草むらなどに入ってマダニに刺されないとも限りません。
そこで今回はマダニに刺されたときの対処法を取り上げたいと思います。
大好きな猫にかまれるのはかまいませんが^^:…マダニには刺されたくありませんからね。
気になる方一緒にみていきましょう。
目次
マダニに刺された時の対処法はこれ
マダニに刺されると様々な感染症にかかる可能性があります。
刺されたと思ったらすぐに皮膚科を受診しましょう!
以下にマダニに刺されて発症する代表的な感染症を上げておきますので参考にしてみてくださいね。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
冒頭のニュースでもご紹介した重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ですが、マダニを媒介にした感染症では、国内でもっとも多く発症しているといわれています。
ウィルスを持ったマダニを媒介にして感染する病気です。
発症初期で発熱、倦怠感、腹痛、食欲低下、嘔吐などと風邪の症状とよく似ています。
症状が進んでいくと、痙攣、意識障害、出血などが起こり、最悪の場合死に至ることもあるといいます。
この3年間の発症数は195人で、そのうち死亡が 48人おり、死亡率がとても高い感染症ですね。
血液等の患者体液との接触で、人から人への感染も報告されているといいます。
有効な薬剤やワクチンもなく、現在は対症療法しかないということです。
ライム病
マダニを媒介してスピロヘータという菌に感染するとおこる病気です。
傷口近くから全身に紅斑が広がり、倦怠感、寒気、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、結膜炎、肺炎、神経症状、血尿など様々な症状が現れます。
抗生物質の投与で治療します。
ライム病はマダニに刺されてから48時間以上経つと感染リスクが高まるとされています。
日本紅斑熱
症状は風疹に似ていて、発疹や発熱の症状が起こるといいます。
2017年の7月に静岡県80代の女性が、日本紅斑熱を発症して死亡しました。
日本紅斑熱は、リケッチア・ジャポニカという病原体を持つマダニに刺されることで発症する感染症です。
2~8日の潜伏期間を経て、高熱や発疹が現れ、重症化すると死に至る危険な感染症です。
ダニ媒介性脳炎
2016年北海道でダニに噛まれて脳炎などを発症して入院していた男性が死亡したというニュースがありました。
国立感染症研究所はダニ媒介性脳炎による死亡例は国内では初めてで、予防対策を呼びかけています。
ヤブの中で作業中にマダニに噛まれ、ダニ媒介性脳炎を発症したとのこと。
麻痺や意識障害、痙攣(けいれん)などの症状が現れ、髄膜炎や急性脳炎を発症して死亡したといいます。
マダニを媒介にした感染症にかかったかどうか検査する方法は?
マダニのウィルスに感染しているかどうかは、血液検査で調べることができます。
マダニを媒介とする感染症は、初期症状は風邪に似ていて勘違いしてしまうこともありそうですね。
風邪かなと思ってもなかなか症状が改善しなかったり、草むらや森林などに行ったりした場合には、マダニによる感染症の可能性もあります。
自己判断は危険ですので、必ず皮膚科などの専門医に診てもらい、血液検査をするようにしましょう。
もし、マダニに刺されているのが明らかな場合は、自分で対処しようとせず、病院で処置を行うことをおすすめします。
マダニに刺されたらまずすべきことは
マダニは人の皮膚に喰いついて口先を深く挿入してきます。
そして、セメント状の物質を出してしっかりと接着してくるんだとか^^;
なんていやらしいダニなんだ!!!
ですから、マダニに刺されたら簡単には取れません。
無理に引っ張ってとろうとするとマダニの頭の部分だけが皮膚に残ってしまい、感染症を起こすことがあるので要注意!
7~10日位放置しているとマダニは充分に血を吸っておなかが一杯になり自然と離れていくといいますが、
そんなに一緒にいたくないですよね、
血を吸っていないマダニの体長は1mm程度ですが血を吸って大きく膨らむと7mm程度まで大きくなるといいます。


24時間以内ならピンセットによる除去も可能だとか!
それ以上になったら周辺皮膚とともに切除することが一般的!
これだと感染症が起こりにくくなるといえます。

マダニ感染症は薬で治る?
マダニを媒介して発症する感染症は重症熱性血小板減少症候群(SFTS)のように治療法が確立していないものも多くあるといいます。
マダニに刺されていることが分かったら一刻も早く皮膚科を受診しましょう。
早くマダニを取り除くことで感染のリスクを減らすことができるからです。
皮膚科を受診するとマダニを取り除き、念のため抗生物質を処方されるそうです。
マダニに刺されないための対策は?
マダニが生息しているといわれる草むらや森林に入ると時は、必ず長袖、長ズボンに靴下をしっかりと履いて肌の露出をできるだけ少なくしましょう。
虫除けスプレーなどをかけておくとより安心できますね。
マダニにも効くと書かれている物を選んでくださいね。
入浴したら身体にマダニがついていないか隅々まで確認するとよいでしょう。
猫や犬からの感染が報告されています。
ペットのダニの駆除もしておいた方が良いでしょう。
まとめ
マダニに刺されえたら自分で取り除こうとせず、すぐに皮膚科を受診して診察を受けましょう。
危険な感染症にかかるリスクがあります。
自己判断は危険ですのでやめましょう。
草むらや森林など、マダニが生息している場所に立ち入るときは長袖、長ズボンに靴下をしっかりと履いて肌の露出をすくなくしましょう。
虫除けスプレーなども使用してしっかり対策をしておきましょう。
マダニの生息地に入った後は、家の中に入る前に上着を脱いでマダニがついていないか確認しましょう。
入浴したら身体にマダニがついていないか隅々まで確認するとよいでしょう。
治療法のない病気ですから気をつけたいですね。