車椅子の移乗で腰を痛めたりしていませんか?
家族が急に車椅子を使うようになってしまい、よく分からないまま車椅子の移乗を行っているという方も多いのではないでしょうか。
統計を取ったわけではありませんが、女性が男性を介護するケースの方が多いと思います。
皆さんが行なっている車椅子の介助の中で、車椅子からトイレ、トイレから車椅子への移乗が一日の中でもっとも多いのではないでしょうか?

重たい男性を女性が介助して移乗するのは大変なことだと思います。
介護の現場でも女性スタッフが重たい男性の利用者を介護することが多いですね。
車椅子の移乗で腰を痛めてしまい、退職してしまう女性スタッフも多いと聞いています。

管理人も、元介護職員として施設で働いていた経験から正しい移乗のやり方を覚えて腰への負担を減らし、腰痛を予防したいという思いで車椅子移乗について勉強していました。
今回は、車椅子の移乗で最も多いと思われるトイレへの移乗について書いていこうと思います。
目次
車椅子からトイレへの移乗方法は?
車椅子からトイレへの移乗について、文章にするととても長くなります。
先に動画を見ていただくと、移乗の流れが掴みやすくなると思います、
手足に麻痺のある方の車椅子からトイレへの移乗について、とても参考になる動画を見つけましたのでご紹介しておきますね!
こちらは重たい人を移乗させるテクニックをご紹介している動画です。
小柄な女性が大柄な男性を移乗させるのに適しています。
管理人もやって見ましたが、介助者との身長差がある方がやりやすいのかなと感じました。
それでは、車椅子からトイレへの移乗方法について解説していきますね。
移乗方法は車椅子の方(要介助者)の立ち上がる力がどれだけあるかによって変わってきます。
車椅子移乗のポイント!
- 手足に麻痺がある場合
- 自分で立ち上がれる場合
- 立つことができない場合
※ここでは、介助をする人を介助者、車椅子に乗っている人を要介助者と呼ぶことにします。
自分で立ち上がれる場合は?
安全に移乗をするためには、できる限りトイレと車椅子の距離を近づけることが大切です。
大まかな流れとしては…
- 車椅子を便器の斜前方から近づける
- 車椅子のブレーキをかける
- フットレストを上げる
- お尻を前方にずらす
- 立ち上がる
- 回転し、ズボンを下ろし便座に腰掛ける
これだけだと分かりづらいかと思いますので、1つ1つを詳しく見ていきましょう!
1 車椅子を便器の斜前方から近づける
家庭のトイレの場合、あまり広くないと思いますので理想的な角度に車椅子をつけられない場合もあります。
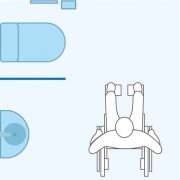
スペースがあればトイレと車椅子のタイヤがある面との角度を15~30度にしましょう。
要介助者に手足の麻痺がある場合は、良い方(麻痺のない方)が便器側に来るように車いすをつけます。
麻痺がなければ向きはどちらでも大丈夫ですよ。
要介助者や、介助者のやりやすい方向に向けてあげましょう。
2 車椅子のブレーキをかける
車椅子のブレーキをかけておかないと立ち上がる際、車椅子が動いてしまい上手く立ち上がれません。
また、バランスを崩して転倒してしまうこともあります。
必ずブレーキをかけるようにしましょう。
3 フットレストを上げる

足を乗せるフットレスト(足を乗せる所)を上げて足を床に下ろします。
これを忘れてしまうと、立ち上がるときに間違ってフットレストを踏みつけてしまい、車椅子が跳ね上がってしまうことがあるので要注意!!
4 お尻を前方にずらす
車椅子に深く腰掛けた状態から立ち上がるのは大変です。
要介助者に、「少し前に出てきてください」などと声をかけて、なるべく浅く腰掛けてもらいましょう。
そうすることで前の方に重心を移動させやすくなり、立ち上がりが楽になりますね。
5 立ち上がる
要介助者に「そのままお辞儀をするように体を前傾して立ち上がりましょう」などと声をかけて立ち上がりを促します。
立ち上がりのポイントは、自分のあごが膝の前まででくるように身体を前に傾けること!
これをしっかりと意識して行うと立ち上がりが楽になりますよ。
このときの介助者の立ち位置は必ず麻痺のある側です。
バランスを崩すのは麻痺のある側がほとんどだからです。
自分で立つことができる方の場合、あまり介助をしすぎると要介助者本人の立ち上がる能力を低下させてしまいますのでバランスを崩したときにすぐに手が出せるよう近くで見守ることが大切ですね。
6 回転し、ズボンを下ろし便座に腰掛ける
立ち上がれたら、良い方の足を一歩前に出し回転しましょう。
ここでズボンを下ろしてもらいます。
麻痺のある方は健側(麻痺していない手)の手で左右交互にズボンを下ろすのですが、できない場合は介助者がズボンを下ろしてあげましょう。
自力で立ち上がれる方でも長時間は立っていられない場合があるからです。
手早くズボンを下ろして便座に腰掛けてもらいましょう
長く立っていられない場合はズボンを下ろさずに一度便座に座ってもよいでしょう。
そこからもう一度立ち上がり、ズボンを下ろしてもOKです!
こうすると、後ろには便座がありますからバランスを崩してもすぐ便座に座ることができて安全です。
自分で立つことができない場合は?
トイレへと移乗する流れは同じです。
ただし、1つ1つに対して心がけるポイントは変わってきますので、再び詳しく取り上げていきますね。
なお、1~3までは自分で立つことができる場合とそう差はありません。
意識ポイントは4以降です^^
1 車椅子を便器の斜前方から近づける
家庭のトイレの場合、あまり広くないと思います。
スペースがあればトイレと車椅子のタイヤがある面との角度を15~30度につけてください。
要介助者に手足の麻痺がある場合は、良い方(麻痺のない方)が便器側に来るように車いすをつけるようにしましょう。
麻痺がなければ向きはどちらでも構いません。
要介助者本人や、介助者のやりやすい方向に向けてあげましょう。
2 車椅子のブレーキをかける
車椅子のブレーキをかけておかないと立ち上がる際、車椅子が動いてしまい上手く立ち上がれません。
最悪の場合、バランスを崩して転倒してしまうことも!
ブレーキは必ずかけるようにしましょう。
3 フットレストを上げる
足を乗せるフットレスト(足を乗せる所)を上げて足を床に下ろします。
これを忘れてしまうと、立ち上がるときに間違ってフットレストを踏みつけてしまい、車椅子が跳ね上がってしまうことがありますからご注意を!。
4 お尻を前方にずらす
介助者は要介助者の前方に位置します。

介助者は要介助者の麻痺側の脇と腰部を支え、前に出るように促します。
この時、「すこし前にでてください」などと声をかけて、できるだけ自分の力で前に出てもらいましょう。
それでも動かない時は介助者がお尻を前に移動させます。
5 立ち上がる
脇とズボンを支えたまま、要介助者に前かがみになるよう促し、できるだけ体を前方に傾けてもらいます。
そうすることで重心が前方に移動してお尻が上がりやすくなり、介助量も軽減されますので「少し前にでてください」や「前かがみになってください」など、声をかけてあげましょう!
本人に立つ気になってもらわないと介助者の負担ばかりが増してしまいますからね。
介護は介助者と要介助者の共同作業と考えることが大切なんです。
たとえ立ち上がることができなくとも、要介助者が介助者にしっかりと摑まることができたら移乗はとても楽になりますよ。
6 回転し、ズボンを下ろし便座に腰掛ける
要介助者の立位がとれた事が確認できたら便器の方にお尻を回しましょう。
介助者は要介助者の上体を支えたまま、ズボンを下ろします。
お辞儀をするように体を前傾して腰をおろします。
介助者は上体と殿部を支えながら便器に要介助者をゆっくりと座らせます。
ここまでが車椅子からトイレへの移乗の手順になります。
用を足してもらい、ここからは、便座から車椅子への移乗になります。
今度はは逆の手順で行ってみましょう。
トイレから車椅子への移乗方法は?
自分で立つことができる場合
大まかな流れとしては…
- 車椅子を便器の斜前方から近づける
- 車椅子のブレーキをかける
- フットレストを上げる
- お尻を前方にずらす
- 立ち上がる
- ズボンを上げて回転し車椅子に腰掛ける
車椅子への移乗動作も1つ1つを詳しく見ていきましょう!
1 車椅子を便器の斜前方から近づける
家庭のトイレの場合、あまり広くないと思いますので理想的な角度に車椅子をつけられない場合もあります。
スペースがあればトイレと車椅子のタイヤがある面との角度を15~30度に着けましょう。
要介助者に手足の麻痺がある場合は、良い方(麻痺のない方)に車椅子をつけます。
麻痺がなければ向きはどちらでも構いませんので、要介助者本人や介助者のやりやすい方向に向けて行いましょう。
2 車椅子のブレーキをかける
車椅子のブレーキをかけておかないと座る際に車椅子が動いてしまい転落の危険性があります。
必ずブレーキをかけておくようにしましょう。
3 フットレストを上げておく
足を乗せるフットレスト(足を乗せる所)を上げておきます。
フットレストが左右に開く場合は邪魔にならないよう開いておくとより安全です。
4 お尻を前方にずらす
「少し前にでてください」などと声をかけ、要介助者になるべく便座に浅く腰掛けてもらいましょう。
重心が前のほうに移動して、立ち上がりが楽になるからです!
5 立ち上がる
要介助者は車椅子の肘掛に捕まってお辞儀をするように体を前傾して立ち上がります。
ポイントは、自分のあごが膝の前まででくるように意識して立ち上がることです。
介助者は麻痺のある側について見守りましょう。
バランスを崩したときにすぐに手が出せるよう近くで見守ることが大切ですね。
6 ズボンを上げて回転し車椅子に腰掛ける
しっかり立つことができたらズボンを上げていきます。
自分で上げられない時は介助者が行ってくださいね。
ズボンが上がったら良い方の足を一歩前に出し回転します。
自力で立ち上がれる方でも長時間は立っていられない場合がありますから、時間がかかるようであれば介助者が手早くズボンを上げて車椅子に移乗してもらいましょう
長く立っていられない場合は、ズボンを上げてから一度便座に座ってもらってもよいでしょう。
そこからもう一度立ち上がり、回転して車椅子に移乗します。
こうすると、2回立ち上がることになりますが、より安全に移乗ができます。
自分で立つことができない場合は?
車椅子へと移乗する流れはだいたい同じです。
ただし、自分で立つことができない場合は介助者の助けが必要になります。
再び詳しく取り上げていきますね。
なお、1~3までは自分で立つことができる場合とそう差はありません。
意識ポイントは4以降です^^
1 車椅子を便器の斜前方から近づける
家庭のトイレの場合、あまり広くないと思いますので理想的な角度に車椅子をつけられない場合もあります。
スペースがあればトイレと車椅子のタイヤがある面との角度を15~30度に着しましょう。
要介助者に手足の麻痺がある場合は、良い方(麻痺のない方)に車椅子をつけるようにします。
麻痺がなければ向きはどちらでも構いませんよ。
要介助者本人や、介助者のやりやすい方向に向けてあげればOKです!
2 車椅子のブレーキをかける
車椅子のブレーキをかけておかないと座る際に車椅子が動いてしまい転落の危険性があります。
必ずブレーキをかけておくよう習慣にしておいてくださいね。
3 フットレストを上げておく
足を乗せるフットレスト(足を乗せる所)を上げておきます。
フットレストが左右に開く場合は邪魔にならないよう開いておくとより安全ですよ。
4 お尻を前方にずらす
介助者は要介助者の前方に位置します。

介助者は要介助者の麻痺側の脇と腰部を支え、前に出るように促します。
できるだけ自分の力で前に出てもらいます。
それでも動かない時は、介助者がお手伝いしてお尻を前に移動させましょう。
5 立ち上がる
脇と腰を支えたまま、要介助者に前かがみになるよう促します。
「少し前にでてください」「浅く腰掛けてください」などと声をかけると良いでしょう。
できるだけ体を前方に傾けてもらうと、重心が前方に移動してお尻が上がりやすくなりますよ。
介助量を減らすには、本人に立つ気になってもらうことがとても重要なんですね。
たとえ立ち上がることができなくとも要介助者が介助者にしっかりと摑まることができたら体重の重い要介助者でも楽に立ち上がらせることができますからね。
6 ズボンを上げて回転し車椅子に腰掛ける
要介助者の立位がとれた事が確認できたらズボンを上げていきましょう。
ズボンが上がったら良い方の足を一歩前に出し回転します。
長く立っていられない場合は、ズボンを上げてから一度便座に座ってもらい、そこからもう一度立ち上がり、回転して車椅子に移乗しましょう。
こうすると、2回立ち上がることになりますが、より安全に移乗ができるのでオススメです。
ここまでがトイレから車椅子への移乗の仕方になります。
最初は難しいと感じるかもしれませんが、慣れる事が大切だと思います。
移乗ができるようになったら!
車椅子からトイレへの移乗ができるようになったら家族と外出してみたいですよね。
当サイトでは車椅子で旅行に出かける際の注意点をまとめた記事を書いております。
車椅子でお出かけを考えている方は参考にしてみてくださいね。

まとめ
いかがでしたか?
車椅子移乗のポイントをまとめると
- 手足に麻痺がある場合
- 自分で立ち上がれる場合
- 立つことができない場合
これらの場合でやり方が変わります
自分で立ち上がることができる場合の大まかな流れとしては…
- 車椅子を便器の斜前方から近づける
- 車椅子のブレーキをかける
- フットレストを上げる
- お尻を前方にずらす
- 立ち上がる
- 回転し、ズボンを下ろし便座に腰掛ける
自分で立ち上がることができない場合は立ち上がりのときに介助を要します。
トイレから車椅子への移乗方法は?
自分で立ち上がることができる場合の大まかな流れとしては…
- 車椅子を便器の斜前方から近づける
- 車椅子のブレーキをかける
- フットレストを上げる
- お尻を前方にずらす
- 立ち上がる
- ズボンを上げて回転し車椅子に腰掛ける
自分で立ち上がることができない場合は立ち上がりのときに介助を要します。
施設と違って各家庭ではトイレも広くありませんよね。
介護も1人で行わなくてはならないことも多いはず!
介助者が腰を痛めてしまう原因は主に移乗だと思います。
安全で腰に負担の少ない移乗方法を知って腰痛を予防したいですね。










