最近、テレビのボリュームが大きくなったといわれたことはありませんか?
話を何度も聞き返したりすることも!
年をとると高い音が聞こえにくなるといわれています。
管理人もお年寄りと接する機会が多いので、気になっています、
今回は高齢者に多い難聴といわれる加齢性難聴についてみていきたいと思います。
目次
年齢以外に特別な原因がない難聴
年齢以外に特別な原因がない難聴を加齢性難聴と呼んでいます。
加齢にともなる聴力の変化
20歳代では高い音も低い音も聞こえています。大きい音も小さい音も聞こえています。
50歳代から高い音が聞こえにくくなってきます。
70歳代では音が大きくても高い音が聞こえにくくなってくるといわれています。
ただ、聞こえ方には個人差が大きいため80歳を過ぎてもよく聞こえる人もいます。
加齢性難聴は誰にでも起こりうる病気
その頻度はというと
- 60歳代前半で5~10人に1人
- 60歳代後半で3人に1人
- 75歳以上で7割以上
といわれていますからほとんどの方が加齢性難聴になっていると考えられます。
加齢性難聴は、聞こえに関する様々な場所が機能低下をきたすための起こります。

耳の穴を外耳、鼓膜の奥を中耳、さらに奥を内耳と呼んできます。
加齢性難聴になると内耳の機能低下が起こります。
さらに、言葉を理解する脳の機能低下も起きてくるといわれています。
内耳の中には渦巻き型をした蝸牛と呼ばれる部分があります。
私たちは音の振動エネルギーを蝸牛の中の細胞が電気エネルギーに変換することで音として聴いています。
蝸牛の中の細胞を電子顕微鏡で見ると白い毛のようなものが見えます。
これは有毛細胞と呼ばれています。
有毛細胞は蝸牛の中に規則正しく並んでいます。この毛がアンテナの役割を果たしています。
振動エネルギーを電気エネルギーに変換して聴神経を介して脳へ伝えているのですね。
この有毛細胞は年をとると折れたり、細胞自体が剥がれ落ちたりして十分に音をキャッチできなくなってくるわけです。
その結果、聞こえが悪くなり加齢性難聴になるといわれています。
蝸牛の渦巻きの手前側で高い音を感じています。低い音は渦巻きの奥で感じています。
加齢性難聴は、両方の耳の蝸牛の障害が同時に起きてくるといわれています。
加齢性難聴はどのくらいの音が聞こえるのか?

- 9,000Hz 年齢に関係なく聞こえる音
- 14,000Hz 40代まで聞こえる音
- 16,000Hz 20代まで聞こえる音
加齢性難聴の方の聞こえ方はこんな幹事になるそうです。動画を見つけましたので聞いてみてくださいね。
加齢性難聴の予防
有毛細胞は一度壊れると再生しないといわれています。
そのため、予防することが大切になります。
加齢性難聴を悪化させる要因は?
- 糖尿病
- 動脈硬化
- 高血圧
- 脂質異常症
生活習慣病が加齢性難聴に関係していると考えられています。
生活習慣病が続くと耳の内耳や脳の血流障害が起きやすくなる。
●禁煙

●禁酒

●騒音

お酒やタバコ、騒音は、活性酸素などの細胞を傷害させる酸化ストレスを発生させ、正常な組織を壊してしまうとか!
それによって加齢性難聴が起こるといわれています。
そして、脳の血流障害が続くと脳が萎縮して認知症を起こしやすくなるといわれています。
加齢性難聴は、高い音が聞こえにくくなる為、一般的に女性の声が聞こえにくくなります。
加齢性難聴の程度
正常
会話中、しびしば聞き返すことがある。
軽度
テレビやラジオの音が大きいといわれたことがある。
体温計の音が聞こえない。
中等度
銀行や病院で名前を聞き逃すことがある。
高度
目の前の電話の着信音が聞き取れない。
軽度の難聴でも会話が聞き取りにくくなり、人との会話が臆病になってきます。
コミュニケーションが億劫になります。
これを放置しておくと認知症に進んでいくという研究報告があるといいます。
認知症テストというものがあります。
フランスで行われた1989年~2014年に65歳以上の3670人を対象にしたテスト です。
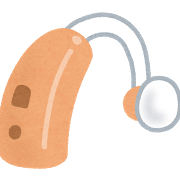
難聴があり補聴器を使っている人と、難聴でも補聴器を使っていない人とでは、明らかな差が出ています。
補聴器を使っている人は、難聴なしの方と比べて成績に大きな差は見られませんでした。
補聴器を使っていない方は、補聴器を使っている方と比べ、明らかに成績が悪かったそうです。
加齢性難聴は早期から対応することで認知症を予防できるといわれています。
加齢性難聴はまだ、確立された治療法がないといわれています。
予防のためには補聴器を使用することが必要です。
補聴器にはいくつか種類があり、耳の状態によって調整が必要になるため、医師の診察を受けてから利用することをお勧めします。
日本耳鼻咽喉科学会の補聴器相談医のいる病院を受診しましょう。
購入は、認定補聴器技能者のいるお店側安心です。
遺伝性難聴
40歳前後で発症して、60歳前後で難聴を自覚する。
難聴の遺伝子検査を受けると良いといいます。
遺伝子検査は限られた施設でしか行われていません。
各都道府県に1人、臨床遺伝専門医の先生がいらっしゃるので、かかりつけの耳鼻科の先生に紹介してもらうとよいでしょう。
遺伝性難聴はまだ根本的な治療はないということです。
補聴器を使用して対応するのですが、聞き取りが困難になってきたら、人工聴覚器という新しい治療があるといいます。
残存聴力活用型人工内耳という新しい治療法が2014年に保険適応になったということで、以前テレビでも紹介されていました。
人口内耳を頭蓋骨に埋め込む事で音が聞こえるようになるというものでした。
医療技術は日進月歩といわれますが今話題のiPS細胞を使った再生医療にも期待したいですね。










